かぶとたいぞうです。
北海道はもう真冬のような気候で、寒さが身にしみます。
いつもこの時期にはタイにいたので、久しぶりの札幌の冬はよけいに寒く感じます。
水道水は冷たく、限りなく0℃に近いでしょう。そんな水で食器を洗うと手がかじかみます。
冬はお湯で食器を洗うのが当たり前だが
我が家は灯油ボイラーなので、家の中のすべての蛇口から豊富にお湯が出ます。ボイラーの火力は強く、設定を最大にすれば、あっという間に90℃くらいの煮たり湯が大量に出てきます。お風呂なんかもあっという間にお湯がたまります。
だから豊富なお湯で食器を思う存分洗えばいいのですが、最近はケチになりました。湯の温度はぬるま湯、蛇口も半分しか開けずチョロチョロ水で洗うのです。節約が身に付いてきました。
昔の人も冬はお湯で食器を洗ったのか
先日、そんな感じで食器を洗いながら、ふと思いました。
「むかし、灯油ボイラーも瞬間湯沸かし器もなかった時代、冬の冷たい水で食器を洗っていたのだろうか」
昔の記憶をたどりましたがなかなか思い出せません。記憶にあるのは流しに備えついているガス湯沸かし器。これのスイッチを入れるといつでもお湯が出たのです。
昔は瞬間湯沸かし器は無かった
でも、私が小学生だった頃はガス湯沸し器は無かったはずです。
ようやく一つの光景を思い出すことができました。
ストーブの上の大きなやかん。
そうです。冬はいつもストーブの上に大きなやかんがのっていて、常にお湯が湧いていたのでした。そのお湯をたらいに入れて水で薄めて適温にし、食器を洗っていたのです。
ストーブの上のやかんのお湯
ご飯を食べ終わったら、めいめいが流しに食器を持っていき、ぬるい湯がたまったたらいに食器をつけるのが我が家のルールでした。
母はその食器のたまったたらいの湯にやかんの熱い湯を足して適温にし、洗剤で食器を洗っていました。
しかしゆすぎは水だったので、洗い終わったあとはストーブで手を温めていました。
ゆすぎは冷たい水だった
「ああ、冷たい」
いつも母はそう言って、真っ赤になった手をストーブにかざしてこすり合わせていました。
今思えば、ストーブの上のやかんは冬の室内の乾燥を防ぎ、お茶を入れ、そして食器を洗うのにも利用されていたのですね。大変便利です。
人間は昔から鉄瓶でお湯を沸かしていた
原始時代のことは分かりませんが、人間はかなり昔から冬は炉に鉄瓶をかけてお湯を沸かしていたのではないかと思います。

今のファンヒーターはストーブの上が熱くならず、やかんは使えません。
我が家のストーブは大型のポット式輻射なのでストーブの上も熱くなります。
今は小さな鉄瓶をのせていますが、どうせならもっと大きな鉄瓶を買ってストーブの上に乗せておき、冬の食器洗いにも使おうかと思いました。
やっぱり鉄瓶
やかんでもいいのですが、やっぱり鉄瓶のほうが趣があります。
さっそくアマゾンで調べたら、本物の南部鉄瓶が1万円で買えるんですね。もちろん日本製です。
1.5リットルならちょうどいい大きさです。
時間をかけて鉄瓶の中が真っ白になるまでしっかりと育て上げようと思います。
ごきげんよう。
【関連性の高い記事】
この記事があなたのお役に立った場合、下の「いいね!」をクリックして頂けると、たいへんはげみになります。
【あわせて読みたい】
同じカテゴリーの最新記事5件
-
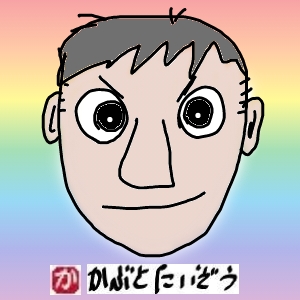
【日本の年金】やっぱり年金はもらえるうちにもらった方がいいと思う。蜃気楼になる前に -
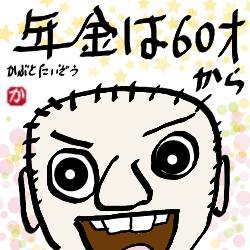
【人生100年時代】みんな100歳まで元気に生きると言う話はどうも嘘らしい -

お盆に娘、息子、3人の孫たちが次々に来て楽しかったけど、みんな帰って一人になると寂しいどころかホッとする -
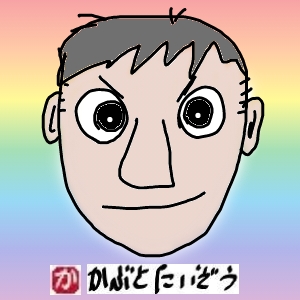
【お盆と孫たち】お盆で孫たちが次々来て嬉しいけど、忙しくてブログが書けず -
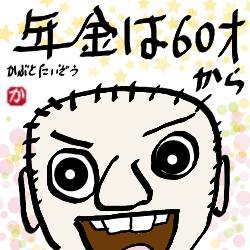
【年金の繰上げ受給】繰り上げで60歳から年金をもらっておいて本当に良かったと思う
「カブとタイ」をいつもお読みいただき、まことにありがとうございます。
著者かぶとたいぞう拝。
記事のカテゴリー/タグ情報
