かぶとたいぞうです。
昨日、北海道でとうとう100人を超える新型コロナ新規感染者が出たというニュースで大騒ぎになっています。

内訳は、札幌市で93人、函館市4人、旭川市3人、小樽市1人、その他18人の合計119人です。圧倒的に札幌に集中しています。
札幌で新規コロナ感染者が93人、GO TOトラベルの影響か
間違いなくGO TOトラベルの影響でしょう。
それと最近は寒いので換気をしていないのも感染者拡大を助長しているような気がします。
私がよく乗るバスは先週ぐらいまでは窓を開けていました。しかし今週からすべて閉めて走っています。札幌の外気は4度以下まで下がり、今週は雪が降っているのです。窓を開けたまま走れば乗客は寒くて死んでしまいます。死なないまでも風邪をひいてしまうでしょう。だからバスの窓を閉めているのは仕方がないと思います。
札幌の路線バスは寒くて窓を閉めたが仕方がない
朝夕の満員バスの中にひとりでも新型コロナの感染者がいればみんなうつるだろうと思いますが、だからといって窓を開けてくれとは言えません。窓を開けたまま走るバスに30分も乗っていれば、ほんとに死んでしまいます。
これからさらに寒くなり、ますます新型コロナの感染者は増えていくと思いますが、果たして北海道の119人、あるいは札幌の97人という数字は世界各国と比べた場合多いのでしょうか。
新型コロナ感染者数が札幌で93人、北海道で113人、世界的に見たら多いのか少ないのか
なんか少ないような気もするのです。検証してみましょう。
先ずは感染者数がひときわ多い米国との比較です。
米国は現在、毎日10万人ぐらいの新規感染者が出ています。米国の人口は3億3千万人です。
米国の1日の新型コロナ感染者数の割合
人口に占める1日の新規感染者数の割合は0.03%です。
北海道の人口は530万人ですから、119人の新規感染者発生率は0.0022%。
札幌の人口は200万人なので97人だと0.005%。
米国、イタリア、北海道、札幌、1日の新規感染者数比較
小数点以下が多くて分かりづらいので、それぞれ10000倍すると、
米国300、北海道22、札幌50の割合です。
こう見ると札幌も北海道も米国に比べたらそれほど多くないと感じます。
同じ計算で、イタリアは人口6千万人、1日の新規感染者数3万人なので0.05%。10000倍して尺度を合わせると500。米国の300を上回ります。こう見ると札幌の50はそれほど多いとは思いません。
札幌で新型コロナに感染する確率
また、確率から言うと、札幌の1日の感染率は0.005%、つまり10万人に5人、2万人人1人の確率です。宝くじに当たるような確率です。
クラスターになるべく近寄らず、いつもマスクをして手洗いを頻繁にすればどうにかなるような気がするのですが、甘いでしょうか。
パタヤにいたときに比べると緊張感が無くなった
私もパタヤにいた時はものすごく慎重でした。札幌に戻ってはや3ヶ月。日本は重症者や死者が少ないのもあって緊張感がなくなってきました。
人はあまりにも長いあいだ緊張感を持続することはできないようです。
スペイン風邪のときも次第に話題にならなくなった
スペイン風邪のときも最初の頃は毎日何人死んだとかの話題で持ちきりだったのに、2年も経てばもうスペイン風邪の話を誰もしなくなったといいます。
別にスペイン風邪の特効薬ができたわけではありません。スペイン風邪が収束したわけでも終息したわけでもありません。
相変わらず一定割合で新規感染者が出て、一定の割合で死者が出たのですが、誰ももう関心を示さなくなったようです。
スペイン風邪の話題に飽きてきたんだと思います。
そして知らないうちに、スペイン風邪は消えた
そして知らないうちにスペイン風邪がなくなったようです。きっと人類に免疫ができたのでしょう。
今回の新型コロナもそのうちに収まるでしょう。そして何十年後には新型コロナも「普通のインフルエンザ」の一つになるのだと思います。
そうあってほしいです。
ごきげんよう。
【関連性の高い記事】
この記事があなたのお役に立った場合、下の「いいね!」をクリックして頂けると、たいへんはげみになります。
【あわせて読みたい】
同じカテゴリーの最新記事5件
-

業務スーパーの合成酒が売り切れ。みんな生活防衛に入っているようだ。ビジネスチャンスはインバウンドにあり -
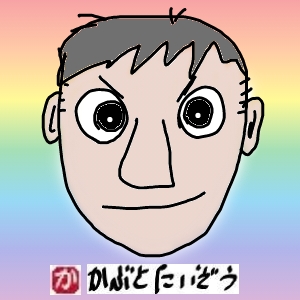
少子高齢化問題も人口問題も介護問題も子育て問題も、旧民法の家の制度を壊したから起きたのかもしれない -

【日本の物価】タイから9ヶ月ぶりに帰国して一番感じたこと。物価が上がり過ぎ。便乗値上げもあるんじゃないか -
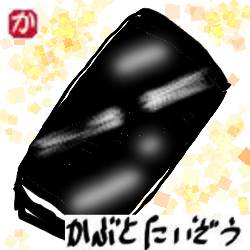
アマゾンを名乗る詐欺っぽいショートメッセージ(SMS)が送られてきた -

【ネット犯罪】詐欺事件のニュースばかり見るが、騙されるほうにも問題があるんじゃないかな
「カブとタイ」をいつもお読みいただき、まことにありがとうございます。
著者かぶとたいぞう拝。
記事のカテゴリー/タグ情報
