かぶとたいぞうです。
今日は価格表示に関して書きます。
消費税が上がったのに表示価格が同じ
昨日、消費税が上がってから初めて近所の大手スーパーで酒を買いました。表示されている価格を見て「あれ?増税前と値段が同じだ」と思いました。いつも買う酒なので増税前の値段を覚えていたのです。
一瞬「元値を下げたのかな」とも思いましたが、よく考えるとぜんぜんちがいました。
税抜き価格だったのです。税抜き価格なら、増税前も増税後も同じです。
本来、価格表示は消費税込みの総額表示が義務付けられています。
たとえば、本体価格が1000円の酒ならば、増税前は1080円と表示し、増税後は1100円と表示しなければなりません。
8%から10%までの間の特例措置
ところが、前回の増税時、消費税を5%から8%に上げた直後に、矢継ぎ早に10%まで上げる計画だったのでその間に限り特別措置がなされたのです。わずかな期間に値札を2回も張り替えるのは大変だ、なんとかしてくれと言う小売店の強い要望を受けての措置でした。
つまり、消費税を10%に上げるまでの期間に限り、税抜きの価格で表示しても良いとしたのです。ただし、別に消費税がかかるということを誤認の無いよう明記することという条件でした。
この特例を受けて、ほとんどの小売店は価格表示を1000円(消費税込み1080円)のように、わざと税抜き価格が目立つように書き換えました。
本来は値札の書き換えが大変だからと言う理由で行なった特例を悪用して、わざわざ税抜き価格を大きく見せる値札を新たに作ったのです。
それでも特例措置に違反していないという理由でギリギリ黙認されました。次の消費税増税までのわずかな期間対応ということで許したのです。
増税がたびたび延期となり外税表示が定着してしまった
ところがその後、消費税増税は2度も延期となり、長期間その特例措置が許されました。わざと税抜き価格を大きく書いて、消費者に安いと誤認させて売るテクニックが定着してしまったのです。
【関連性の高い記事】
心ある企業は特例措置を使わず、正々堂々と総額表示をする中、消費者の誤認を誘うテクニックを使い続ける業者も依然残りました。
でも、そのような姑息な手段を用いることができるのも消費税が10%に上がるまでの間だけだと思って我慢していた人も多かったのではないかと思います。
10%になったのに税抜き価格で表示する姑息さ
ところが、10月1日に消費税が10%に上がり、特例措置を使う必要がなくなったにもかかわらず、いまだに税抜き価格で表示している店がたくさんあるのです。
1000円(消費税込み1100円)のように税抜き価格を大きく書いて税込みの総額表示を小さく書いています。最近目が悪くなったので、小さい字で何が書かれているのか読めません。まったく姑息です。
値札を書き換えるぐらいなら、本来の義務である総額表示になぜ戻さなかったのか。
実は特例措置は2度の消費税増税延期の間に有効期間が延長され、2021年3月まではいちおう有効なのです。これは値札の印刷などが間に合わない零細小売店向けの猶予期間であって、悪用期間ではないのです。
大手企業もいまだに税抜き価格
昨日行ったスーパーはイオンです。大企業です。値札の印刷ができないような規模ではありません。それどころか、今回の消費税増税に合わせて、わざと小さな字で10%の税込価格を書き加えた値札にちゃんと取り替えているのです。
税抜き価格ばかりが大きく、税込の総額表示は字が小さすぎて読めませんでした。値段の後ろに何か書かれているのは分かるのですが、字が小さすぎるので年寄りはみんな読めないのではないのでしょうか。
こんな感じです。
1000円(消費税込み1100円)
今は年寄りが多いのにそんなことをして恥ずかしくないのでしょうか。姑息ですね。まったく姑息です。どこまで消費者の誤認を誘うテクニックを使うのか。
われわれ日本人は本来、正直でまじめで正々堂々とした態度を好む民族です。いつまでも人をだますようなテクニックを使わないで欲しいです。
なさけない。実になさけないです。
ごきげんよう。
【関連性の高い記事】
この記事があなたのお役に立った場合、下の「いいね!」をクリックして頂けると、たいへんはげみになります。
【あわせて読みたい】
同じカテゴリーの最新記事5件
-

業務スーパーの合成酒が売り切れ。みんな生活防衛に入っているようだ。ビジネスチャンスはインバウンドにあり -
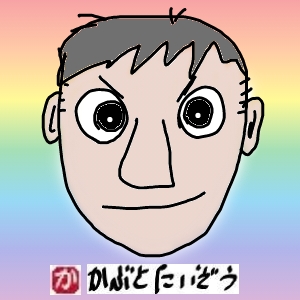
少子高齢化問題も人口問題も介護問題も子育て問題も、旧民法の家の制度を壊したから起きたのかもしれない -

【日本の物価】タイから9ヶ月ぶりに帰国して一番感じたこと。物価が上がり過ぎ。便乗値上げもあるんじゃないか -
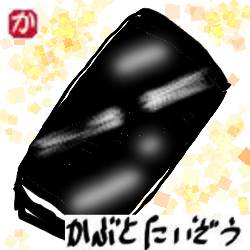
アマゾンを名乗る詐欺っぽいショートメッセージ(SMS)が送られてきた -

【ネット犯罪】詐欺事件のニュースばかり見るが、騙されるほうにも問題があるんじゃないかな
「カブとタイ」をいつもお読みいただき、まことにありがとうございます。
著者かぶとたいぞう拝。
記事のカテゴリー/タグ情報
